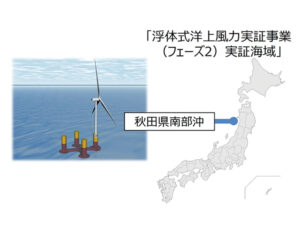【農業×風力発電】「陸上」転用へPoC、小型「浮体式交差軸風車」のOKYA
2021/12/08

特許を持つ小型の「浮体式交差軸風車」を武器に、この技術の陸上への転用に向けて開発と実証実験(PoC)を進めているのがOKYA。同社の菅野優社長に、「交差軸風車」の特長や農業分野での商用化計画などについて聞いた。
交差軸風車で
水陸の風力発電に貢献
株式会社OKYAの社名は「風が吹けば桶屋がもうかる」が由来です。茨城県東海村で今は1人でやっています。自然エネルギーの風力で動くヨット型ロボットが起点ですが、ここから着想した技術を使ってもらえるように事業開発しています。
今、再生可能エネルギーが注目されていますが、日本ではあまり風況が良くなかったり、浮体式風車はあまり揺れには強くなくて、浮かべにくいところもあります。また、風が安定的に吹いてないので、無風状態から吹き始めの時にプロペラの起動性が良くないといった問題もあります。これらの問題に着目して、自分のアイデアを生かしたいと考えています。
――主力商品・サービスと、その強みは。
横軸型の風車で、回転軸と風向が交差する小型の「交差軸風車」と交差軸風車用のブレードを開発しています。垂直軸風車を横に倒した形に近いものです。まだ導入実績はなく、開発、実証試験の段階です。平地のみならず、水上での展開を構想しています。「浮体式交差軸風車」は浮体式風車設備として特許を取得済みです。
交差軸風車用に考案した抗力型、揚力型を両立した開閉式ブレードは、微風時は起動性が良く、強風時は高いエネルギー効率が得られます。そして洋上における交差軸風車は浮体の動揺に影響されない稼働を見込んでいます。
交差軸風車のメリットは、風車の受風面積の設計自由度を得られることです。プロペラ型の受風面積はブレードの長さで決まります。一方、交差軸風車の受風面積は、回転径と軸方向の長さの掛け算で、適用ケースに応じて設計できます。
一つのアイデアとして、回転径をそれほど大きくせず、軸方向に長い風車を作ることを念頭に置いています。スリムで長いローターは空きスペースを有効活用して設置できます。まだアイデアと開発だけで、実績がありませんので、早く実績をつくっていきたいと考えています。
PoC用は直径1m×長さ2m
2022にも農業向けに商用化
最初に手を付けたいと思っているのは、陸上の農地、水田地帯での導入です。今年の実証実験では、風車の直径が1m、長さが2mのものを用意しています。風速ごとの発電電力量データを取得する計画です。風車の発電電力量は風を受ける面積に比例しますので、逆に、どれぐらいの規模の発電をするかによって、サイズが決まりますので、「これぐらいのサイズを作りましょう」と提案できると考えています。
耕作地帯、特に水田地帯は遮蔽物がない平野が多いのではないでしょうか。圃場整備されていると土地が矩形で、排水路周辺の非作付け域はターゲットになり得ると考えています。
――主な提供先は農業従事者となりますか。
そうですね。
――特許出願済みの開閉式ブレードを適用した交差軸風車ですが、実用化のめどは。
農地法など法的なことを今、確認中です。電気の供給方法がクリアになれば、2022年か23年には置ける(商用化できる)と考えています。発電機や風車のパーツについては、垂直軸の風車用に発電機などを提供している会社と協議しており、調達先は確保してあります。
――小型風力発電業界での事業展開をなさっていますが、競合他社をどう意識していますか。
水平軸風車とは別のものとして使っていただけるといいと思います。風力はエネルギー密度が小さいため、より広い面積で風を受ける必要があります。水平軸風車で受風面積を大きくしようとすると、ブレードが長くなり、タワーが高くなり、基礎が大きくなります。ローターの回転数は少なくなるため増速機もギア比の大きいものへの変更が必要になるかもしれません。これらが必要ない交差軸風車は比較的低コストで作ることができると考えています。
――ビジネスモデルは。
導入先の農家が売電収入を得ることをイメージしています。農家側には初期投資が必要なく、売電収入で喜んでいただけるのではないかと考えています。そしてわずかながらでも再生可能エネルギーの発電量比率が増えることが望ましいと考えています。
――政府の「2050年カーボンニュートラル」宣言をどう受け止めていますか。
当社の場合は、どうやって手頃な値段で発電設備を提供できるのかということを考えています。当社の商品は小型風車ですので、メインストリームにいるわけではありませんので、興味を持って見ているというところです。
――御社にとって「追い風」ですか。
はい。「農業×風力発電」によって、わずかながらでも再生可能エネルギーの発電量比率が増えることに貢献したいと思います。
話を聞いた人
株式会社OKYA
代表取締役 菅野優氏

取材・文:山村敬一

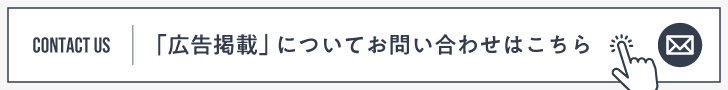
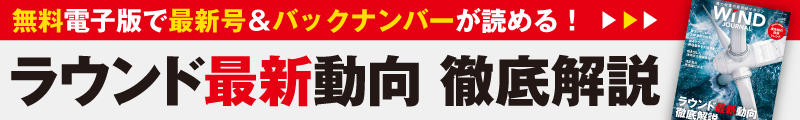



 出典:
出典: