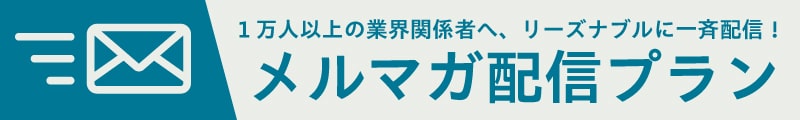洋上風力、事業環境整備の議論を本格化 年内に具体策をとりまとめる方針
2025/09/12

政府は、三菱商事が3海域から撤退したことを受けて、洋上風力発電の電源投資を確実に完遂させるための事業環境整備についての議論を本格化する。9月11日の有識者会議では、年内に具体策をとりまとめる方針を示した。
メイン画像:第2ラウンド「秋田県八峰町・能代市沖」
海域占用期間
40〜50年程度まで延長を検討

第2ラウンド「新潟県村上市・胎内市沖」
経済産業省と国土交通省は9月11日に合同会議を開いた。洋上風力第2、第3ラウンドの選定事業者からは、国に対して追加支援を求める要望が出されている。これまでの会議では、海域占用期間を現行の30年から延長を可能とする方向で合意している。いまの制度では、風車の建設や撤去に要する期間を考慮すると、実質的に20年程度しか商業運転ができない。このため、風力の技術の進歩に合わせて、海域占用期間を40〜50年程度まで延長することを検討する。
洋上風力第2、第3ラウンドの選定事業者からは、このほかにも一定期間の固定収入を保証する「長期脱炭素電源オークション」への参加や、売電価格への補助、落札後の風車メーカー変更の明確化などを求める声がある。しかし、国の公共事業などの入札では、落札後に条件を変更することはない。入札で選定されなかった事業者や、応札しなかった事業者にとって不公平になるためだ。
第2、第3ラウンド
条件変更の判断基準を提示
11日の会議では、第2、第3ラウンドの条件変更する際の判断基準として、(1)政策措置の適用の必要性・合理性、(2)公募における競争の要素に与える影響、(3)政策措置の適用前後における公募占用計画の一体性に与える影響の3点を示した。海域占用期間の延長については、公募占用計画の一体性を損なわないと判断したと説明している。
判断基準の「政策措置の適用の必要性・合理性」については、政策措置が、エネルギー基本計画、再エネ海域利用法の目的などに合致するか、総合的に国民全体の利益につながるか。政策措置が、電源横断的かつ一般的なものである場合、他の電源種を含め、他の再エネ発電事業者との公平性が確保されているかを議論すべきとしている。
「公募における競争の要素に与える影響」については、 供給価格(国民負担の大きさ)、事業実施能力(事業実施体制、資金・収支計画、事業スケジュール、発電設備の施工・維持管理・撤去の方法、サプライチェーンの強靭性、事業のリスク分析と対応など)、地域調整・経済波及効果(関係行政機関との調整能力、漁業等との協調・共生、国内・県内への経済波及効果)を議論すべきとしている。「政策措置の適用前後における公募占用計画の一体性に与える影響」については、選定事業者が、選定当初の計画(発電容量、事業スケジュールなど)から一体性を保って事業を継続できるかを具体的な判断基準として示している。
第1ラウンドの3海域は、FIT制度のもとで売電価格を20年間固定する条件で公募したが、三菱商事は「建設費の高騰により採算性が確保できないと判断した」と説明している。再公募では、市場価格に一定の金額を上乗せして売電できる制度の適用を検討している。政府は、事業環境整備についての具体案を年内にとりまとめる方針だが、すでに入札を実施した第2、第3ラウンドの条件変更が最大の焦点だ。
DATA
取材・文/高橋健一