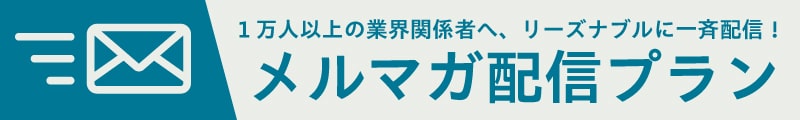世界最大の浮体式事業を推進する韓国。日本が鑑(かん)とすべきもの、轍(てつ)とすべきものとは
2025/07/24

韓国は、日本政府の目標を40%上回る「2030年までに14.3GWの案件形成」を目指す。昨年末に750MWという世界最大の浮体式洋上風力発電案件の事業者を選定した。隣国に学ぶべき点は何なのか。海外事情に詳しい専門家がわかりやすく解説する。
メイン画像:韓国済州市沖の洋上風力発電所。
浮体式の一大市場の日本
隣国で先行する大規模事業
昨年末に第3ラウンドの選定結果が発表され、日本の洋上風力発電市場は、20年の秋田・能代港湾区域の最終投資決定を「商業規模の案件形成元年」ととらえた場合、これまでに実に5GWを超える案件が形成されました。アジア圏において先行する台湾と比べても、わが国は年平均1.3GWと遜色ないペースで市場が発展しています。浮体式に関しても、日本は排他的経済水域の広さから、約952GWの潜在的発電容量(自然エネルギー財団 2023)を誇る一大市場です。
お隣の韓国では、昨年末に計1.9GWの選定事業者が公表され、このうち750MWが浮体式のバンディブリ洋上風力発電所です。エクイノール(ノルウェー)が受託したこの発電事業は、韓国初にして世界最大の浮体式案件として、世界的にも耳目を集めています。日本の浮体式大規模実証の発電容量45MW、現在世界最大の浮体式事業(英国沖・ハイウィンド・タンペン洋上風力発電所)の発電容量88MWと比べても、同事業の規模が突出しています。
比較分析から見えてくる
韓国政府の野心と覚悟
浮体式洋上風力発電市場に関して日本と韓国の現状をPEST分析すると、黎明期にあるという点で、両国には類似点が多く、またそれぞれ独自の強みがあるといえます。違いがあるのは、政府の取り組み姿勢と国内供給網の整備状況です。韓国には、陸上・洋上風力向け主要機器メーカーに加え、浮体関連設備を製造可能な造船所・鉄鋼所が比較的多く存在します。係留索を除いて広範な供給網が構築されており、多くのメーカーは、アジア太平洋経済圏における洋上風力発電設備の一大製造拠点化を目標に事業を展開しています。国内外の市場を見据えた供給網という土台を持っているからこそ、政府による大規模案件組成へのインセンティブや、地方自治体による積極的な投資誘致といったリスク選好度の高い政策実行を可能にしているようです。
欧州資本の洋上風力デベロッパー、EPCコントラクター、メーカーといった企業にとっても、韓国は浮体式事業に参入するうえで比較的理想の条件がそろっています。それは、(1)着床式と比べて遜色ない政府による大規模浮体式への投資インセンティブ、(2)生産能力・価格競争力・品質ともに実績のある国内供給網の存在、(3)欧州基準に準じた認証制度が採用されている点などです。昨年12月初旬以降、韓国政治が混迷を極めるなか、MOTIE(韓国産業通商資源部)は当初の予定通り同月下旬に24年度の競争入札の結果を公表しました。この政策遂行は、韓国政治の安定性に懸念を抱き始めた海外のステークホルダーに対する、信頼回復のための明確な意思表示と受けとめられています。
日本の大手メーカーが19年に風力発電事業から撤退したことで縮小した国内供給網の復活の道のりは、当然険しいものです。日本政府が一定のローカルコンテンツ条項を義務化(公募占用指針に得点化を明記)し、国内メーカーが「日本政府はやる気だ」と安心して洋上風力事業に参入できる環境を整える必要性があることは論を待ちません。一方、国産化義務は外資による投資を減速させる諸刃の剣という側面があり、さじ加減が難しいのも事実です。
私は、日本の洋上風力発電産業を黎明期から支えてきた事業者や施工会社のみなさまが、大きな事業リスクを認識しつつも、長期的視野を持って当該事業に献身的に尽力される姿を間近で拝見してきました。国内供給網の復活は、価格競争力の改善につながり、案件形成の蓄積は、国内外ステークホルダーの工事対応能力の向上につながります。正のスパイラル効果を生み出す起爆剤は、常に政府のコミットメント(覚悟)であることは、洋上風力発電の黎明期だった1990年代の欧州の歴史が証明しています。
以上の考察は、日韓両国の浮体式洋上風力発電における数多くの相違点のうち、ごく一部を挙げているにすぎず、一国の優劣を語ることを意図していません。しかし、韓国の先行事例をつまびらかに研究することは、日本の浮体式市場の発展に大きく利することになると考えます。世界的にも比類なき規模の潜在的発電容量を有する日本で今後蓄積する国内外のノウハウが、近い将来、他国にとって成功事例研究の対象やベンチマークとなる日が来ることを信じてやみません。
PROFILE
風海鳥2004
海外を中心にプラント建設業界に20年以上在籍。洋上風力産業に関しては、APAC圏市場の黎明期(2010年代)からさまざまな工事案件に従事してきた専門家。
WIND JOURNAL vol.8(2025年春号)より転載