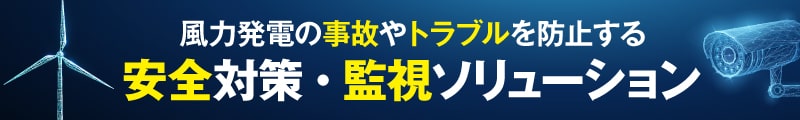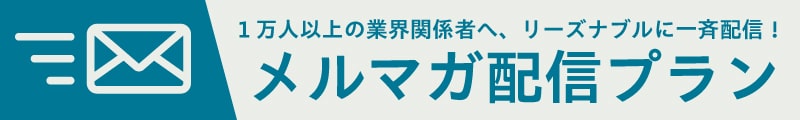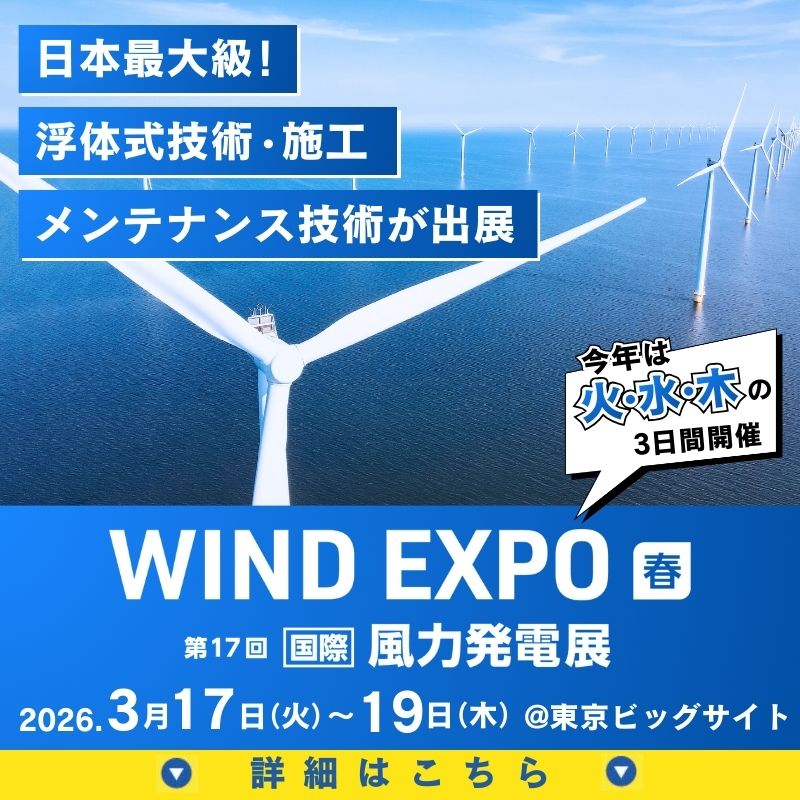日本貿易会の安永会長 洋上風力の事業環境整備「官民が連携して議論すべき」
2025/09/25

三井物産の会長で日本貿易会の安永竜夫会長は9月17日の定例記者会見で、洋上風力発電の事業環境整備について「官民が双方で勉強して案件を実現していくには何が必要かを協議していくことが必要ではないか」と述べた。
1.技術的、経済的な困難さが増してきている
2.官民が連携して 議論する必要性を強調
技術的、経済的な困難さが
増してきている

洋上風力第2ラウンド「新潟県村上市・胎内市沖」
三井物産は、洋上風力第2ラウンド「新潟県村上市・胎内市沖」の事業に参画している。17日の定例会見で、記者からの質問に対して安永氏は、個別の事案について触れることは難しいので一般論として申し上げると前置きしたうえで、「洋上風力を取り巻く環境は日本のみならず世界的に非常に厳しい状況にあると言わざるを得ません。技術的、経済的なプロジェクトの困難さが増してきていることは事実だと思います。より大きな発電量を求めれば、大型化を余儀なくされます。例えば、台湾で建設が進んでいる大型の洋上風力は、土台を含めたポールの高さが120m、ブレードの直径が200mの風車を建設しており、厳しい気象条件の中で維持管理がさらに難しくなります。また、日本国内にはサプライチェーンが存在せず、ブレード(羽のようなパーツ)は欧州から輸入し、ナセル(風力タービンの中核部分)も国産化には何百機と継続的に作っていくという規模感がある程度コミットされないとサプライチェーンが成り立ち得ませんので、市場規模をある程度考える必要があります。また、インフレもあり設備投資額が物凄く膨らんできていることも事実です」と述べ、洋上風力発電の事業環境が困難な状況であるとの認識を示した。
官民が連携して
議論する必要性を強調
そのうえで安永氏は、「こうした環境の中で、官民で実現可能性を話し合って、どの程度なら設備費、建設費を低減できるのかといったさまざまな工夫を事業者側もやらなければならないと思いますし、どのような環境に合わせた柔軟な制度設計が可能なのかといったことを政府にも検討してもらい、官民が双方で勉強して案件を実現していくには何が必要かを協議していくことが必要ではないかと思っています」と述べ、官民が連携して議論していく必要性を強調した。
DATA
取材・文/高橋健一